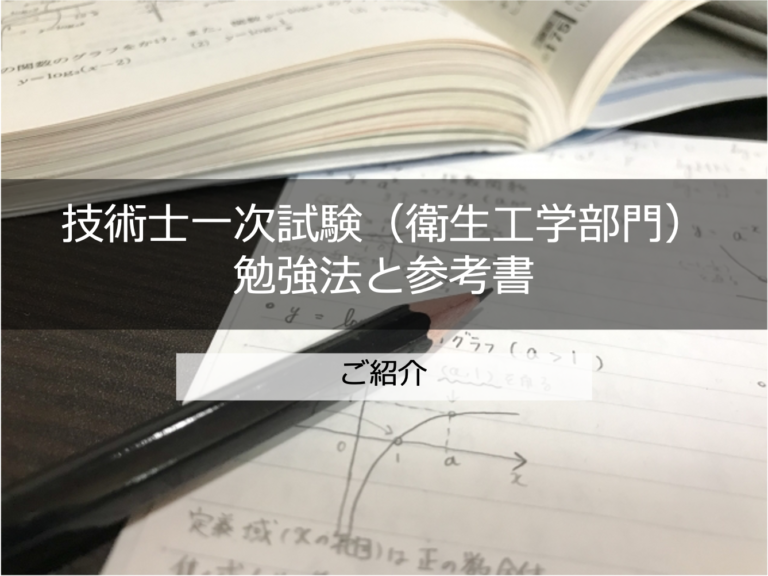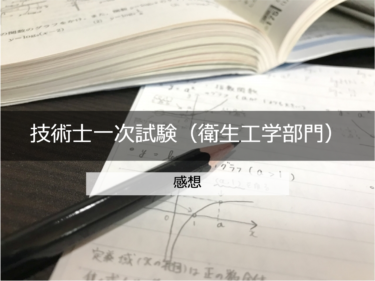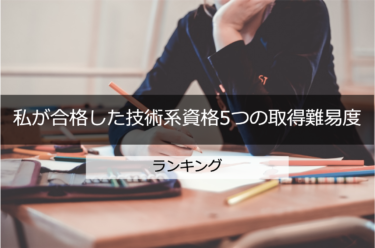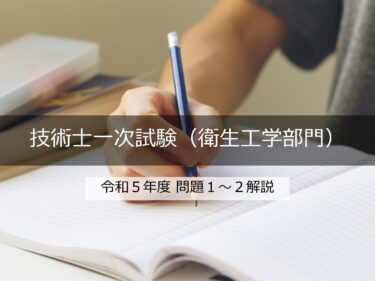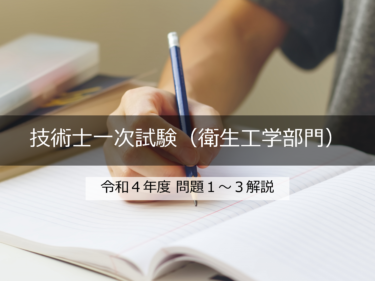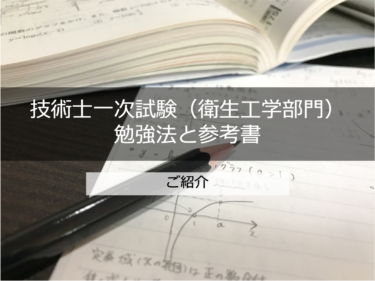今回は、技術士第一次試験(衛生工学部門)の勉強法と参考書を紹介します!
私は、2021年に技術士第一次試験を受験し、自己採点の結果合格見込みです。
専門科目の得点は21/25点と、まずまずの点数でした。
実は私は、今でこそ衛生関係の業界に属していますが、今年の春までは全く別の業界に所属しておりました。
また、学生時代の専門は化学工学でしたので、衛生工学に関する知識はほとんどありませんでした(それでも共通する部分はあるので、学生時代の知識が全く役に立たなかった訳ではありませんが、)
そんな私でも、それなりの点数をとることができましたので、その勉強法や参考書を来年以降の受験生にむけて解説し、役に立てていただきたいと思います。
——————————————————————————————-
(2024/2/10追記)
技術士第一次試験(衛生工学部門)の過去問解説があまりに少ないので、私自身で作成して販売しています。
今のところAmazonとメルカリでのみ販売していますので、安く過去問の解説が欲しい方は探してみてください!
Amazon:
本当にお買い得ですので是非ご検討ください!!
私が使用した参考書4冊
ここからは私が実際に使用した参考書にスコアをつけながら紹介していきます!
まず、新技術開発センターが作成している過去問の解答解説集です!
評価: 4
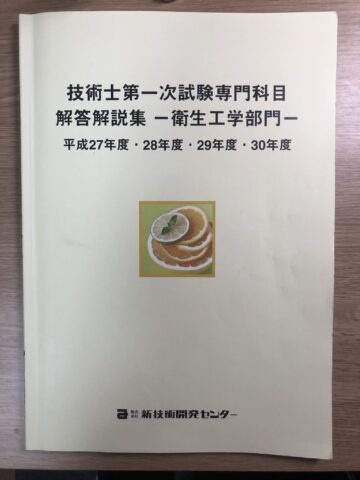
衛生工学部門の近年分の過去問を解説している本はこれしかないと思います。
値段が少々お高い(4000円)のですが、その価値は十分あります。
2年前以上の過去問解説は上の写真のように4年分まとめて販売されているのですが、1年前の過去問解説は1年分だけで販売されていて少々割高ですので、手が出しにくい方は私が作成した過去問を購入していただければと思います。
Amazon:
受験が決まった場合はまずこの本を購入することをおすすめします。
正直、解説がめちゃめちゃ詳しく書かれているかと聞かれたら、そうでもない部分もあるのですが、粗で全体をつかむには十分だと思います。
続いて、こちらの参考書です。
評価: 3.5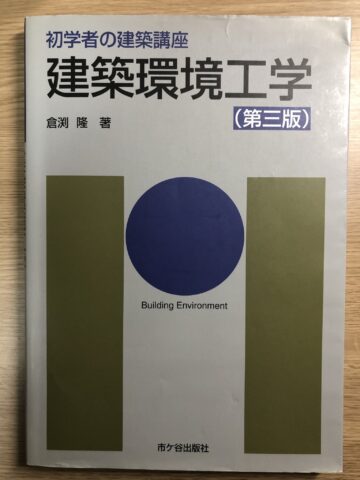
衛生工学初学者の私でもわかりやすく書かれた参考書です。
おそらく、環境工学部や建築学部の1,2年生を対象に書かれたものだと思います。
図やイラストが多くて大変助けられました。
先ほどの新技術開発センターが出している過去問の解説を読んでも理解できなかった部分や、解説がそもそもない部分は、この参考書を読んで理解を進めました。
> 一応リンクを添えておきます
同様にこちらの参考書も購入しました。
評価: 2.5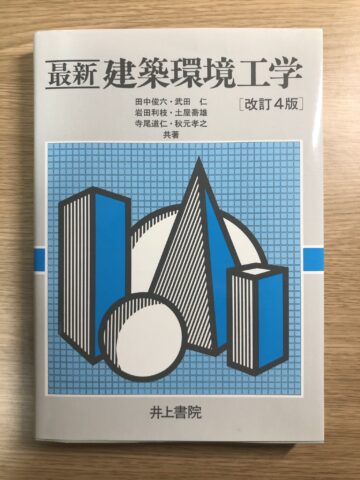
こちらの参考書は「初学者の建築講座 建築環境工学(第三版)」の補助として購入しました。
「初学者の建築講座 建築環境工学(第三版)」よりは少し文章が固い参考書です。
たまに使用しましたが、基本的には「初学者の建築講座 建築環境工学(第三版)」で解決しましたので、そこまで出番はありませんでした。
水処理関係の参考書はこちらを使用しました。
評価: 3.5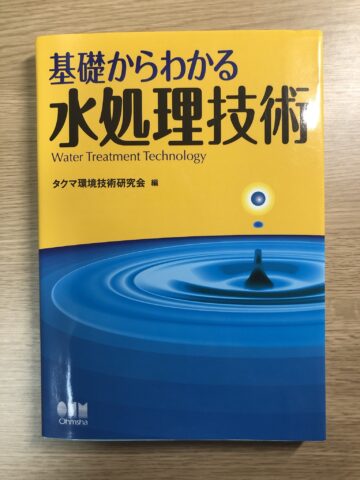
排水の生物学的処理や物理・化学的処理が一通り網羅されているため、試験に出題される排水処理の問題で理解できない部分があれば、この本で調べました。
> 購入はこちら
イラストも多いので便利だと思います。
私はこの4冊を使用して、専門科目の試験に挑みました。
廃棄物処理やダイオキシン類の知識は実務を通して学習しているので、参考書は購入せず、わからない部分はネットで調べました。
勉強方法
次に私の勉強方法を紹介いたします!
その前に、技術士第一次試験の専門科目の問題のクセを知ることが大事かと思います。
・問題は選択問題で、過去問からの再出題率は高め
自分の得意分野の問題に的を絞って、過去問を繰り返し解く
ことが合格の近道だと考えます。
それを踏まえて勉強の流れとしては、
② 自分が得意そうな分野と不得意そうな分野を見分ける。不得意な分野はもう捨てる(10問までは捨てられます)
③ 新技術開発センターの過去問題集をもう1度解き、わからない部分は他の参考書を読んできちんと理解する。
④ 日本技術士会のHPから直近の過去問をダウンロードして解く
まず、受験が決まったらすぐに、新技術開発センターが作成している過去問の解答解説集を購入しました。
最初はほとんど解けませんでしたね笑
自分に業務に関する数問だけ解けて、他の問題は見たこともないものばかりでした。
とりあえず、4年分解いてみると、案外自分の知識で解ける問題があったり、同じような問題があったりすることに気が付きました。
私の場合は、熱環境、空気環境(流体)、水質管理、廃棄物処理、資源循環は「まー勉強すれば解けるようになりそうかなー」という手応えでした。
一方で、音環境、日照・日射、光環境は知識が0に近かったので、最初から捨てました。
その後、新技術開発センターの過去問を、自分が解けそうな分野に絞ってもう一度解き直しました。
ただ、今度は問題を1問1問理解しながら解き進め、わからない部分は参考書やネットで調べて、確実に知識を蓄えていきました。
この過程が一番大変で時間がかかったような気がします。
最後に、日本技術士会のHPから直近の過去問を3年分印刷して解きましたが、この時点で合格ライン、つまり得点率50%は超えていました。
勉強時間は、
1回目の新技術開発センター過去問:15時間
2回目の新技術開発センター過去問:20時間
過去問3年分:15時間
合計:50時間
くらいです。
まとめ
今回は技術士第一次試験(衛生工学部門)の勉強法と参考書を紹介しました。
なかなか受験者数が少なく、参考書も出回っていない試験ですので、どうやって勉強すれば良いかわからない人も少なくないかもしれません。
私は来年か再来年に、技術士二次試験を受ける予定です!
同じ目標の方がいらっしゃれば一緒に頑張りましょう!