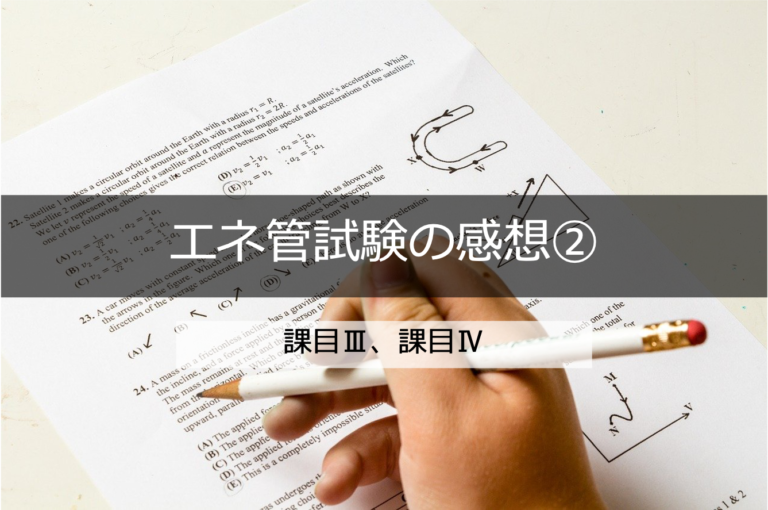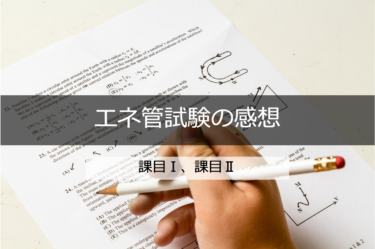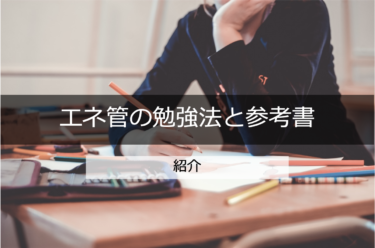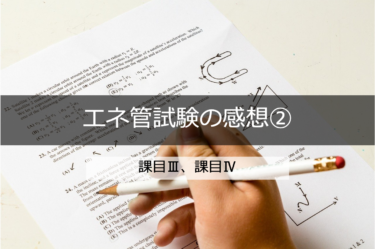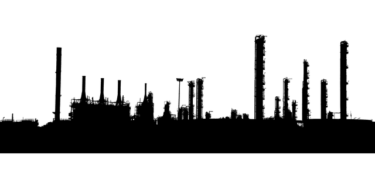せっかくなので、エネルギー管理士試験の3時限目と4時限目の試験の感想もしていきたいと思います!
1時限目と2時限目の感想記事はこちらです。
それでは続きの感想を始めます!
3時限目 熱利用設備及びその管理
この課目も、2時限目の熱と流体の流れの基礎とともにエネルギー管理士試験の鬼門として扱われているようです。
この課目は4つの必須問題と2つの選択問題から構成されていて、時間内に6つの大問を解く必要があります。
必須問題
大問11, 12:計測及び制御
大問13, 14:ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン
選択問題
大問15 熱交換器・熱回収装置(選択)
大問16 冷凍・空気調和
大問17 工業炉、熱設備材料(選択)
大問18 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置
私は実務で熱設備に携わっているため、大問15と17を選択しました!
この3時限目の試験ですが、私めちゃくちゃ得意なんです。
得意といいますか、実務でボイラータービンを見ているので、過去問解いていたらすぐに知識が定着するような感じです。
この時限は基本的に知識ゲーなので、知っていればコンスタントに得点が狙えます。
2時限目でランキン不在に戸惑わされたのに対し、この課目は余裕を取り組むことができました。
ただ、大問12の調整弁の構造に関する問題はあまり自信ないですね、、
6年分の過去問でも一回も見なかった気がします、なかなかコアな問題でした。
あと、大問14のガスタービンの問題もちょっと怪しいですね、、
それ以外は過去問で見たことがあるような問題ばかりだったので、そこまで難しいとは思いませんでした。
2時限目は時間が足りなかったのに対し、この課目は解き終えるのに30分以上時間が余ったので、十分見直しをすることができました。
ちなみに私は早く解き終わっても早く退出せずに、必ず時間いっぱい見直しに時間を使う派です。
これは学生の時からの癖ですね。
4時限目 燃料と燃焼
やっと最後の課目です。
エネルギー管理士試験はとにかく長いです!!
4時限目は燃焼計算がメインな気がするので、試験直前にお菓子を食べて頭を回復させます。
この課目は3つの大問から構成されています。
大問8, 9:燃料及び燃焼管理
大問10 :燃焼計算
戦略としては、大問10の燃焼計算をほぼ完答し、大問8,9でちょろちょろ穴埋め問題を正解しようと考えていました。
この4時限目ですが、公害防止管理者(大気)とボイラー技士2級で勉強した知識がそのまま使えるので、過去問を流しただけでそこまで勉強していませんでした。
一応前日に、大問8, 9を過去問5年分解いて、知らなかった知識や抜けていた知識はノートにまとめてました。
そして、試験開始し、問題見てびっくりしました。
穴埋め問題、ほとんど昨日ノートにまとめたやつやん!!
大問8, 9の穴埋め問題は全部で29問あったのですが、そのうち16問がたった2ページのノートにまとめた内容でした笑
これまで生きてきて、ペーパー試験はそれなりに受けてきましたが、ここまで的中したのは初めてだったかもしれません。
逆にいうと、前日に勉強していなかったら16問は悩みながら解いていた可能性があるということになりますが、、笑
まあ、運も実力のうちということです笑
もしくは、大問8, 9は毎年同じような問題が出ているだけなんですかね。
大問10の燃焼計算は、炭素と水素だけでなく、窒素が含まれている燃料に関するものだったので、少しいやらしい問題でしたが、冷静に考えればそこまで難しくないかと思いました。
ただ、問題最後に出現してきた「燃料削減率」という単語ですが、正直初めて見ました。
結構一般用語なんですかね?
定義がわからなかったです。
また、解答を見直ししていると、四捨五入した値を計算に使用し、解答が0.01だけずれている箇所があることに気が付きました。
やはり見直しは大事ですね。
それにしても、エネルギー管理士試験の解答って0.01だけズレていても不正解になるのでしょうか。
2時限目の熱と流体の流れの基礎とかは時間ギリギリで焦っていたので、0.01だけズレていることが発生してそうで怖いです、、
4時限目は運もあり高得点が狙えそうです。
まとめ
1日ずっと試験だったので、めっちゃ疲れました。
高い受験料を支払っているので、一発で合格したいところです。
私の会社は合格すると奨励金をくださいますが、受験料は自腹なので、、
今年は10月に公害防止管理者、11月に技術士一次試験を受験予定なので、ここで転けたくないという思いもあります。
また、受験勉強で工夫したことや自分なりの受験のポイントがあれば、記事にしたいと思います!